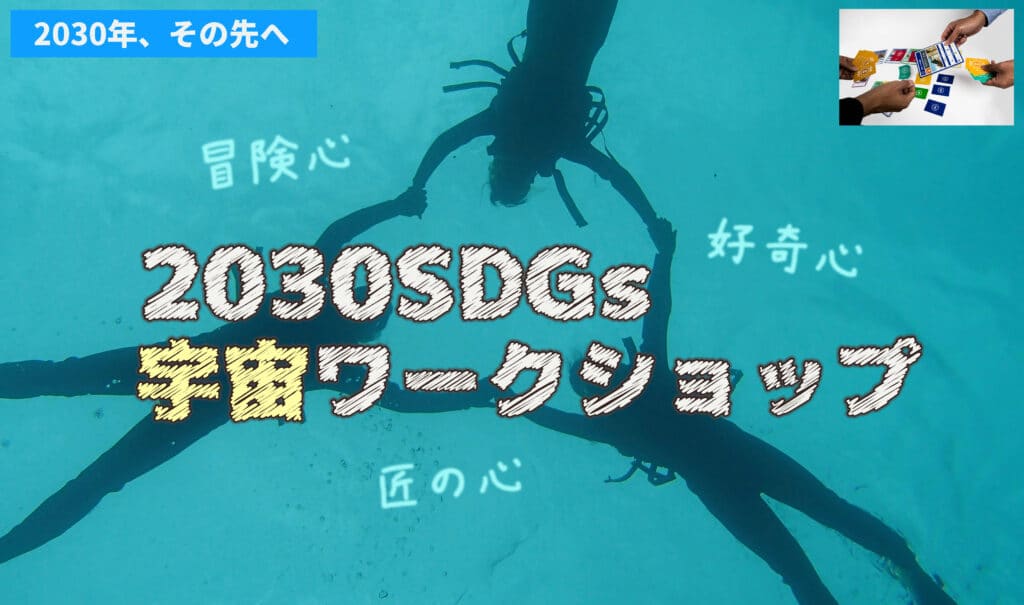「宇宙」という言葉を口にすると、多くの人が「夢があっていいね」とか「ロマンだね」と言います。たぶん、それは「自分には関係ない世界の話」だと思っているからでしょう。
でも本当にそうなのでしょうか?
この記事では「宇宙は自分には関係ない」と思っている方が、宇宙にどう向き合えばいいのかを【宇宙×教育】の視点で書いてみたいと思います。
【この記事を読んでわかること】
- 宇宙への夢を追いかける
- 科学技術の進歩で分かってきたこと
- 悲観から希望へ
- 宇宙の見方を変える
- おすすめのワークショップ
宇宙への夢を追いかける
宇宙を使った教育活動は、全国各地の教育機関や団体が行っていて、各々が思い描く目標を実現しようとしています。
- わが町からロケットを打ち上げたい
- わが校の生徒に人工衛星を作らせたい
- わが子を宇宙飛行士にしたい
- 地球外生命体を発見したい
実に夢のある話です。
一方で、現実離れした遠い世界の話。自分には関係ないし、面白そうだけど役に立たないよね、と多くの人がそう考えているのではないでしょうか。
ここで少し見方を変えてみましょう。

科学技術の進歩でわかってきたこと
人類はいろいろな知識を身につけ、次々と新しい技術を生み出し、私たちは作り出された便利さの中で、生活をしています。
例えば、地球を観測することで、数十年に一度の大洪水、数百年に一度の地震、数万年に一度の○○といった報道ができるようになりました。
また、地球上では人類が頂点に立つ生命体であること。宇宙ではとても珍しい存在かもしれないこと。さらに、自らの手で自然の営みを狂わせているかもしれないことも、わかり始めました。
このような発見はすべて、科学技術の進歩によるものです。
そして、科学技術の進歩により、いまのような生活が、そんなに長続きしないかもしれないという事実にも、気づき始めました。だから「持続可能な開発目標(SDGs)」が必要だと叫ばれているのです。
悲観から希望へ
日々報道される地球上の出来事は、とても悲観的に聞こえます。
もちろん、地球の歴史からすると、ごく当たり前の現象が起こっているだけとも言えますが、人類が手に入れたテクノロジーが原因の一つであることも間違いではなさそうです。
国際宇宙ステーションに人が住み、毎月のようにロケットが打ち上がり、宇宙からさまざまな写真が送られてきて、私たちは日常的にその様子を見ています。
でも、そんな力が人類あるのなら、もっと人類がハッピーになれる方向に、その力を使う事ができるのではないでしょうか。
そんな可能性を、現実味を持って知ることが、いま求められているのかもしれません。
地球を守るため、人類を救うために宇宙へ飛び出していく人たちを描いたアニメ物語は、もう「夢」や「ロマン」だけの世界ではないのです。
宇宙の見方を変える
国際宇宙ステーションから見える地球は青くて美しい。
そして国境は見えません。
この会話からあなたは、そこに自分がいるという感覚を持てますか?
太陽系を飛び出した探査機ボイジャーから見た地球は、
ゴマ粒よりも小さく見えます。
あなたは、自分の居場所がそこにしかないという現実に気づいていますか?

私たち人間が住む地球は、宇宙の中ではとてもちっぽけな存在です。
なのに、私たち人間はそれに気づいていない。
いや、気づいていないフリをしているのかもしれません。
そこで、みなさん、
ちょっと立ち止まって「宇宙の視座」で、いまの生活を違った角度から見直してみませんか。
おすすめのワークショップ
『SDGs』で掲げられた17の目標は、日々の改善活動だけでは達成できないと言われています。
なので『Transforming our world』という取り組みが、真に求められているのです。
2015年9月に国連で採択された合意文書『Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development(我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ)』が、SDGsの正式名称である。
そして【バックキャスティング】という考え方も推奨されています。
バックキャスティングとは、もともと環境保護の分野で使われ始めた言葉です。
現状の社会や環境ありきでものごとを考えると、どうしても望ましい環境に行きつかない事があります。その時に、はじめにあるべき環境・ありたい環境を挙げ、そこに行きつくためのギャップや方策を考える、というアプローチです。
とはいえ、あるべき環境を思い描くのも難しいもの。ついつい現状の延長線で考えてしまいます。
そこで、大きく発想を転換するために使えるのが「宇宙の視座」です。
満を持して登場したのが、いま話題の「2030SDGsゲーム」を使ったこちらのワークショップです。
2030SDGs公認ファシリテーターと一緒に、宇宙の視座で10年先、50年先、1000年先の私たちのあるべき姿を想像しながら、今日からの行動変革につなげるヒントを探究してみませんか?
ワークショップの詳細は、こちら をご覧ください。
ここまでお読みくださいまして、ありがとうございました。
これからも「宇宙×教育」に役立つ情報を発信していきます。
(この記事はnoteのリライトです。)